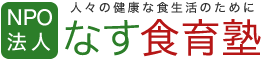なす食育塾Blog > 元気のらクラブ
カテゴリー:元気のらクラブ
まだまだあった夏野菜
- 2012-11-09 (金)
- 未分類
最後まで残っていた家庭菜園のトマト。今日撤去しました。
赤くなりきれないトマトが何と4キロもありました。盛夏のころより数が多いみたいな・・・・
 捨ててしまうにはもったいないし、そうだピクルスはどうだろう。
パプリカとたまねぎをカットして、少し塩をまぶしておく。
捨ててしまうにはもったいないし、そうだピクルスはどうだろう。
パプリカとたまねぎをカットして、少し塩をまぶしておく。

 あまり酸っぱいのが苦手なので酢を控えめにして、仕上がりを楽しみにしましょ。
でもまだ3キロもあるし・・・・どうしましょうか?
あまり酸っぱいのが苦手なので酢を控えめにして、仕上がりを楽しみにしましょ。
でもまだ3キロもあるし・・・・どうしましょうか?
 捨ててしまうにはもったいないし、そうだピクルスはどうだろう。
パプリカとたまねぎをカットして、少し塩をまぶしておく。
捨ててしまうにはもったいないし、そうだピクルスはどうだろう。
パプリカとたまねぎをカットして、少し塩をまぶしておく。

 あまり酸っぱいのが苦手なので酢を控えめにして、仕上がりを楽しみにしましょ。
でもまだ3キロもあるし・・・・どうしましょうか?
あまり酸っぱいのが苦手なので酢を控えめにして、仕上がりを楽しみにしましょ。
でもまだ3キロもあるし・・・・どうしましょうか? - Comments: 0
- Trackbacks: 0
産業文化祭に出店
- 2012-10-22 (月)
- 未分類
昨日の日曜日は最高のお日和。市の産業文化祭への参加で、揚げパンと玉こんにゃく、飲み物のブースを出させていただきました。
今回は明日葉村の若者も一緒に参加、小4、高校生を含めた総勢12名で楽しくやってまいりました。



 若者たちも大きな声で販売ができて、自信につながったようです。高校生も熱心に参加してくれました。お馴染、子ども店長は今回は裏方に徹して、大人と同じ働きができました。
おかげで早々に完売となり、ご褒美は畜産フェアのバーべQ。応援の人たちも加わって、わい!ワイ!と賑やかなバーべQ大会となりました。
ご協力いただいた皆さんお疲れさまでした。
若者たちも大きな声で販売ができて、自信につながったようです。高校生も熱心に参加してくれました。お馴染、子ども店長は今回は裏方に徹して、大人と同じ働きができました。
おかげで早々に完売となり、ご褒美は畜産フェアのバーべQ。応援の人たちも加わって、わい!ワイ!と賑やかなバーべQ大会となりました。
ご協力いただいた皆さんお疲れさまでした。







 若者たちも大きな声で販売ができて、自信につながったようです。高校生も熱心に参加してくれました。お馴染、子ども店長は今回は裏方に徹して、大人と同じ働きができました。
おかげで早々に完売となり、ご褒美は畜産フェアのバーべQ。応援の人たちも加わって、わい!ワイ!と賑やかなバーべQ大会となりました。
ご協力いただいた皆さんお疲れさまでした。
若者たちも大きな声で販売ができて、自信につながったようです。高校生も熱心に参加してくれました。お馴染、子ども店長は今回は裏方に徹して、大人と同じ働きができました。
おかげで早々に完売となり、ご褒美は畜産フェアのバーべQ。応援の人たちも加わって、わい!ワイ!と賑やかなバーべQ大会となりました。
ご協力いただいた皆さんお疲れさまでした。




- Comments: 0
- Trackbacks: 0
最後の夏野菜
- 2012-10-16 (火)
- 未分類
いよいよ秋野菜から冬野菜へと移る今の時期、まだまだ夏野菜も健在です。
最後の夏野菜を使って大量消費をしましょうか。
ピーマン、あまとう、ゴーヤ、なす、トマト、ししとう、いんげん、パプリカ、たまねぎ、じゃがいもも加えて、「夏野菜の焼き浸し」一気にいってみましょう。
いつもは「揚げ浸し」にしていたのだけれど、今回はオーブンで焼いてみましょう。
天板いっぱいの野菜にオリーブオイルをまぶし、220°で20分ほど焼きます。
それを漬け汁に一晩漬けこんでいただきます。
漬け汁:しょうゆ、酢、みりん、酒、すべて同量。
 少し取り分けて、チーズ焼きにしましょ。
少し取り分けて、チーズ焼きにしましょ。
 最後の夏野菜、無駄なく美味しくいただきました。
最後の夏野菜、無駄なく美味しくいただきました。
 少し取り分けて、チーズ焼きにしましょ。
少し取り分けて、チーズ焼きにしましょ。
 最後の夏野菜、無駄なく美味しくいただきました。
最後の夏野菜、無駄なく美味しくいただきました。
- Comments: 0
- Trackbacks: 0
こんなに育ちました
- 2012-06-12 (火)
- 未分類
久しぶりの畑。
新米ファーマーのくせに、畑への足が遠い・・・。
先輩から「そろそろ○○○○をやった方が良いですよ。」なんて助言を受ける有り様。トホホ。
梅雨の合間を縫って今日こそ畑へ!
じゃがいもがこんなに大きく育っていました。
 しかし、こんないたずらも・・・・
しかし、こんないたずらも・・・・
 せっかく育ち始めたサトイモが・・・カラスのしわざ。その後ネットかける対策 で対抗。
七味用のとうがらし「栃木三鷹」を植える予定で空けておいた畑が、手違いで苗が手に入らないことに。さて、この後何を植えましょうか。
他に茄子、枝豆、トウモロコシも順調に育っています。
せっかく育ち始めたサトイモが・・・カラスのしわざ。その後ネットかける対策 で対抗。
七味用のとうがらし「栃木三鷹」を植える予定で空けておいた畑が、手違いで苗が手に入らないことに。さて、この後何を植えましょうか。
他に茄子、枝豆、トウモロコシも順調に育っています。

 このソラマメは人様のもの。本当に空に向いてなっているのを見て、ついパチリと盗み撮りしてしまいました。
このソラマメは人様のもの。本当に空に向いてなっているのを見て、ついパチリと盗み撮りしてしまいました。
 しかし、こんないたずらも・・・・
しかし、こんないたずらも・・・・
 せっかく育ち始めたサトイモが・・・カラスのしわざ。その後ネットかける対策 で対抗。
七味用のとうがらし「栃木三鷹」を植える予定で空けておいた畑が、手違いで苗が手に入らないことに。さて、この後何を植えましょうか。
他に茄子、枝豆、トウモロコシも順調に育っています。
せっかく育ち始めたサトイモが・・・カラスのしわざ。その後ネットかける対策 で対抗。
七味用のとうがらし「栃木三鷹」を植える予定で空けておいた畑が、手違いで苗が手に入らないことに。さて、この後何を植えましょうか。
他に茄子、枝豆、トウモロコシも順調に育っています。

 このソラマメは人様のもの。本当に空に向いてなっているのを見て、ついパチリと盗み撮りしてしまいました。
このソラマメは人様のもの。本当に空に向いてなっているのを見て、ついパチリと盗み撮りしてしまいました。
- Comments: 0
- Trackbacks: 0
なす食育塾Blog > 元気のらクラブ
- Feeds
- 管理メニュー